小学校に入学して、保護者が不安なことランキング上位に入る「登下校」
「安全に登下校できるか」だけでなく、そのうちトラブルが起こってくることも。トラブルを起こしたり、巻き込まれたり、もめたり、よくあることです。
ここで、保護者の方に、知っておいてほしいことがあります。
「登下校の責任は保護者にある」ということです。これを認識しているかどうかで、解決に向けてスムーズに進むかが変わってきます。
長引かせないためには、保護者の方が自分事として捉えることからはじまります。保護者の方が登下校に付き添い、お子さんの登下校を把握して指導する、その上で先生に相談という形がよいでしょう。
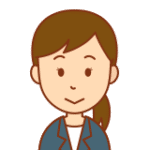
ずばりとお答えするので少し厳しく聞こえるかもしれませんが、教員歴20年以上、1年生担任8回で250人以上を見てきたからこそのお話をお伝えします。
1年生に下校トラブルが多い理由
登下校時のトラブルは、低学年のトラブルの中で最も多いと言ってもよいほどです。
低学年の下校トラブルの理由は単純です。
- 大人がいない
- 下校時の友達は気が合うなど関係なく毎日固定されている
突発的に行動してしまうことも多く、トラブルを起こすことが多いです。大人の目がないので、トラブルを未然に防ぐことができません。
トラブルが起こっても、自分たちで解決することはまだ難しいです。
登下校を共にする友達は、気が合う・合わないは関係なく、近所に住んでいるからという理由で、毎日一緒に過ごすことになります。
子どもは素直で世界も狭ので、「一緒にいなければならない」「仲良くしなければならない」という思いが自然と身に付きます。
この離れられない関係・離れない関係が中学年くらいまで続きます。
低学年から下校の友達とトラブルが続いていれば、おのずと中学年まで続いてしまいまうのですね。
やっかいなことは、子どもだけでなく、保護者の思いもつもり積もってしまということです。
保護者にとっても悩ましい登下校のトラブルとなります。
高学年になると、距離感や空気を読むようになり、気の合うもの同士で下校するようになります。
高学年の下校トラブルと、低学年の下校トラブルは別です。
中学年の下校トラブルは、低学年を引きずり、気づかせていく段階になります。
トラブルが中学年まで続きやすい原因
1年生の間に、下校トラブルはすぱっと解決したいところです。しかし、毎日繰り広げられる子どもだけの世界を変えることは難しいです。
このようにしたらトラブルが起こらないということは断言できません。
しかし、低学年・中学年の下校トラブルを見てきて、長引くトラブルには特徴があることに気づきました。
①保護者の方に登下校は保護者の責任だという認識が弱い
②保護者の方が大人になりきれていない
③お子さんが特定の子に固執してしまっている
④お子さんが突発的に行動してしまう
特徴を知ることで、長引くトラブルを回避してほしいと思います。
登下校はお家の方の管理下という認識が弱い
登下校は園と同じで保護者の方の責任であるという認識が弱いと、他責になりやすく子どもがいつまでも成長しない姿が見られます。
登下校は放課後になるので、お家の方の管理下なのです。
文部科学省からも先生の仕事をはっきりとさせるためにもきちんと示されています。
しかし、保護者に気を遣い、はっきりと言わない学校が多いです。
学校外で起こした友達同士のトラブルであっても、学校内に持ち込まれるので、見過ごすこともできません。
学校がはっきりと言わなかったり、学校が仲介に入ったりすることで、保護者の責任であるという認識が弱まります。
特に、登校班をつくったり、下校班をつくったりして登下校している学校は「学校が見てくれるものだ」という傾向が強いです。
例えお伝えしたとしても、「とは言っても保護者だけでは見きれないから学校も見てよね」という認識の方も一定数おられます。
「学校の行き帰りだから学校が見るものだ」という思いがある場合は、トラブルが起こりやすかったり、長引く可能性が出てきます。
他人任せになり、自分ごととして解決にあたろうとしないからです。
他責に陥り、事の解決からそれてしまいがちです。トラブルが長引くか、たびたび起こる可能性が出てくるのです。
登校班でのトラブル事例
登校班がある場合は、先生に相談すれば話し合いの場を設けます。登下校に関しては保護者の方の責任とはいえ、学校は安全に登下校してもらうために、知らん顔はしません。
保護者は学校の責任、登校班が悪いと余計に勘違いしやすくなっています。
「保護者の言い分あるある」で多いのが登校班です。
・登校班の人のことを怖いと言っている!
・登校班の人が歩くのが速い!
など、要望ばかり訴えてしまうことです。
登校班は善意で成り立っています。
1年生だけで登校するのは心配ですし、保護者が毎日送り迎えするのは大変ですよね。
だから、登校班がつくられているのです。学年が上がった時には下の子を見てあげましょうということで、地域でつくられている組織です。
登校班がない学校も多数あります。その場合は、保護者が近所の方にお願いに上がるということもあるのです。
登校班の意味を理解すると、登校班に対する見方も変わってきます。
・毎朝集合場所までは見に行こう
・しばらくは一緒に歩いて登校してみよう
など、考えが変わるかと思います。そして、登校班の人への伝え方も変わるかと思います。
・いつもありがとう
・もう少し歩くのをゆっくりしてもらえないかなあ?
保護者が積極的に登下校に関わることになります。保護者の目が入ると、上級生が変わることもあります。これは無理だな、、、と諦めがつくこともあります。
入学直後の下校トラブル事例
低学年では下校班で帰ることが多いです。
ところが、下校グループを学校で作成し、入学当初に先生が近所まで送るといういわばプラスαのことをしていることで、学校がするのが当たり前だと勘違いを生み出していることがあります。
1年生担任と決まって、「大変だ!」と真っ先に思い浮かべるのが、入学直後の下校です。
名前と顔が一致しない上、住んでいるところ、通学路まで把握できていません。入学してしばらくは、この送迎に関してエネルギーを費やされる日々です。
下校班に誤りがあれば訂正のために連絡をいただけたらよいです。
しかし、保護者が本来すべき送迎という認識が弱いと、思わぬ方向にいくのです。
・先生が道を間違って長い距離歩かされた!
・分けていたグループを間違えられた!
・放課後児童クラブに行く(休む)のを間違えている!
激高される方がおられます。
道をはさんで、「こっちに渡らせておけや!」と怒鳴られた先生もいました。お子さんたちとの1年間の楽しみな気分がどんよりです。
- お家の方が迎えに来ていただくか、一人でも帰れるように練習しておく
- 毎日お子さんに放課後児童クラブに行くか休むかについて確認する
- 放課後児童クラブを休む場合はどのように帰るかを確認する(特に初めて休む場合)
最低限、ここまでは行っていただけなければ入学後の下校でトラブルが起こりやすいです。
下校の間違えは安全性にも関わりますので、ご家庭でしっかりと確認しておくことが大切です。
器物破損のトラブル事例
学校が見てくれるものだという認識になっていると、我が子がトラブルを起こした時に、課題がすり替わってしまいます。それは、そのお子さんにとっても教育上よいとは言えません。
[お子さんがご家庭の庭に勝手に入って物を壊して逃げてしまった]
・先生は道に立ってくれないのですか?
・あそこの学校の先生はいつも立って見てくれているらしい
・スクールサポーターを増やしてくれたらいのに
・家庭に丸投げでいいね、先生は何かしてくれたのか。
人様の家に入り、物を壊して逃げたという、本来考えなければいけないことからずれてしまっています。
忙しくて、下校のことまで考えられない保護者も多いかと思います。
しかし、これでは、お子さんが反省して次に活かすという成長の機会が奪われるどころか、マイナスの影響になってしまいます。
保護者の不満は学校に向けられるので、学校と考えのすれ違いが起こり、「学校はわかっていない!」「学校は何もしてくれない!」となってしまいます。
子どものトラブル解決の前に、保護者の方の思いのたけの解決が先になり、どんどん本来の解決から遠のいてしまいます。
最も効果的な方法は、お子さんを連れて謝りに行くことです。お子さんに謝らせるだけでなく、保護者が一緒に謝る姿を見て、お子さんの心に響くのでしょうね。
これで、トラブルを起こさなくなったお子さんは多いです。
- 心配ならば見に行こう!一緒に歩こう!
- 気になることはお願いベースで
- 動いてみたけどうまくいかない場合は先生に相談を
お家の方が大人になりきれない
トラブルが長引く原因は、お家の方が子どもと同じ土俵に立つ・同じ目線に立つからだと言っても過言ではありません。下校トラブルにおいても同じです。
客観的に大人の視点からアドバイスをしてあげなければ、子どもの考え方が成長していきません。
近所の子ども同士で帰ることは多いですが、仲良しさんが年下の子たちばかりで、そこに混じって帰ることでトラブルを引き起こしていたことがありました。
その年下の子たちは、同じ学年で、一人だけ混ざってトラブルを起こしているわけですので、その子が、同学年の子たちと帰れば課題は解決しそうです。
ところが、友達をつくることが苦手で、いつまでもそのグループから離れられないのです。そして、それは子どもだけでなく、お家の方も同様でした。
お家の方がお子さんにアドバイスするどころか、年下グループの子たちに対して文句が出てくるのです。それではいつまで経ってもお子さんは同学年の友達をつくろうとならないです。
年下グループの子たちは成長していっているのです。いつまでも親子で園の時代のままでいるということです。
お家の方が大人の振る舞いを見せてくださることで、ことがスムーズにいくことがあります。トラブルがあった時も、ぐっと飲み込んで、その場を沈めてくれています。
集合場所でふざけて友達をけがさせた子たちがいました。
少しの期間、自宅療養となりました。それだけ大事ですし、大変なことをしたので、保護者の方々も、謝罪はもちろん、お家に通ってできることはないか尋ねてあれこれ探っていました。
そのけがをされたお子さんのお家の方は当たり前ですがご立腹ですので、受け入れてもらえないことも多かったのですが、それでも、登校できるまでできる限りのことをされておられました。
けがをさせたのだから当たり前と言えば当たり前なのですが、なかなか根気強くされており、保護者の方の誠意を見ました。
このような場合、一言言いたいことが出てきたりもします。現に言ってしまう方もおられます。
また、他責の気持ちが出てきて、責任を逃れたくなるものです。
あるあるは、学校のせいにするということです。近所の方とうまく付き合いたいために、最終的に学校を悪者にしてお互いにおさめるというパターンです。
そこを、「けがをさせたのは我が子」ということをしっかりと受け止めて、お家の方が責任もって最後まで対応されておられました。
疲れたり、子どもをかばいたくなってしまう気持ちもあるかと思います。
・うちの子だって
・うちの子だけではない
・なぜうちの子ばかり
と出てくるものです。そこをこらえられるのは、大人です。子どもはこれをよく言います。
しかし、やった事実に対して向き合わなければ、解決策が出てきませんし、前に進まないです。これをお家の方が理解し、いろいろな思いがありながらも、ぐっと飲み込めるかにかかっているのです。
- 課題に向き合うお家の方の姿が子どもの成長につながると信じて!
- 愚痴などは大人の世界の中にとどめておく
固執してしまっている
学年が上がってもよくあるトラブルの原因が、固執してしまっている場合です。
トラブルが続くなら他にも近所の子がいるのだから、違う子と帰ればよいのですが、それがなかなかできないようです。特に女子によく見られます。
そのようなよく揉めるグループは、たいてい低学年から何か揉めています。
「あの子が一人になったらかわいそう」と嫌なことを受ける側が相手のことを考える子が稀ですがいます。
しかし、それは稀で、ほとんどは、固執してしまっています。クラスが変わってそれぞれ友達関係が変わっていても、そこに入りたがる子がいます。
・新しい友達をつくるのが苦手
・その子(グループ)に惹かれるものがある
・新しいことへのハードルが高い
理由は様々ですが、本人は理由がわかっていないことも多いでしょう。
他にもたくさん楽しく過ごせそうな子がいること、名前を挙げたり、軽く斡旋もすることがあります。
しかし、戻ってきてしまったり、抜け出せずに、トラブルを続けるということがあります。
友達はその子だけではない、他の子と過ごすともっと楽しいことがあると言うことがまだ経験値が浅いためわからないのですね。
中には、仲間外れしているようで、距離を置きたいことを言えない子もいます。“お友達と仲良く”という言葉を素直に受けとめていているのですね。その場合は、「仲間外れ」と「距離を置くこと」の違いや、「距離の置き方」を教えてあげる必要性があります。
しかし、なかなか煮え切らないことも多いです。性格的なもので見守るしかなさそうです。年齢と共にだんだんわかってくることもありますし、そのような優しさで友達関係に苦労することもあります。
しかし、それはその子のよさでもあると考え、「いつでも味方だからね」と見守り支えてあげることが大切でしょう。
しびれをきらして相手のことを否定したり悪く言ったりしそうになりますが、そこはこらえる高度な大人な対応が求められます。悩みが続くようならば先生に相談するのもよいでしょう。
先生からお話ししてもらえると納得するかもしれません。また、クラス替えなどの考慮にも上がってきます。
突発的な行動に出てしまう
・考えるよりも先に体が動いてしまう
・親や先生など大人の監視の下でしか止められない
同じことを何度言っても繰り返してしまうお子さんの特徴です。登下校は、まさに子どもだけの場面となり、体がのびのびと思いのままに動いてしまうようです。
友達が注意したとしても止めるだけの威力はありません。何かことが起こってから、指導となり反省する、その繰り返しとなってしまいます。
単独でトラブルを起こすことも多いですが、友達が関わってしまうトラブルも多くお家の方は大変かと思います。毎日同じメンバーとなるので、相手が同じになってしまいがちで、相手の保護者の方が激怒されてしまいます。
相手がいるトラブルを起こした場合は、すぐに子どもを連れて謝りに行くということが大事です。
相手のお家の方は、いじめに発展しないか、大きな事故が起こらないかなど、今後のことを気にされます。ですので、トラブルを起こしてしまった子どもの保護者の方が、トラブルに関して知っているのか、そして、きちんと子どもに注意しているのかを気にされます。
お家の方の真摯な姿を見て安心される方は多いです。
登下校に関わらず、考えて行動できるように少しずつ指導して、身に付けていくことが必要となります。とは言っても、登下校中に突発的に動くことで、大変危険なことにもなり得ます。
危なさを合わせて厳しく注意することも必要ですが、何かあってからでは大変です。保護者が一緒に登下校することも検討した方がよいでしょう。
トラブルを長引かさない対応策
①長い目で見て何をすべきかを考える
②大人としての立ち振る舞いをする
③登下校の様子を見に行く・付き添う
登下校のトラブルに限らず、①②は鉄則です。この2点ができていないばっかりに、トラブルが長引いたり、ことあるごとにトラブルになったりしてしまいます。
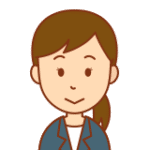
相手がいる場合は、お家の方が納得できないばっかりに、相手の保護者とのやり取り、子どもたちへの聞き取りなどが数日間続くことがあります。
子どもは本当にこのトラブルの話し合いを望んでいるのかなと思うことがほとんどです。特に低学年では、保護者の方の納得感を得るために子ども同士の話し合いがもたれることが少なくありません。
よろしければ、下記のブログをご参照ください。
トラブルを起こしてしまった時
子どもがトラブルを起こすと認めたくないあまりに様々な方向へ向かってしまう保護者の方がおられます。
- 理由を追及する保護者
- 自分が責められた気分になる保護者
理由を追求する保護者は、「何も理由なしにしないはず!」と大人の考えで、自分が納得いく回答を得られるまで問いつめてしまうのです。
「理由なんてない」「つられて」と言う場合も多いのです。例えあったとしても「なんとなく」という言葉に変わってしまうのです。
後先考えず、悪いと思ってやっていなければ、理由がなくて当たり前と言えば当たり前です。やったことが事実ならば、悪かったことを話できたことをほめてこれからのことを確認して終わればよいのです。
しかし、それでは許されず、様々な理由を考え始めるのです。
- 誰かをかばっているのではないか
- 誰かに口止めされているのではないか
- 以前に○○だったか・・・(妄想)
追及され続けた子どもはどうするでしょうか。
- 保護者の納得いく回答を探しながら答える(事実と異なる)
- 面倒くさいと思い、今後話さなくなる(嘘をつく)
こういった流れになりますよね。
子どもが悪いことをしてしまった時に、それを認めることで、自分が責められているように感じられる保護者もおられます。
自分の育て方を責められていると感じるだけでなく、自分自身を責められていると感じられる方もおられるのですね。
ですので、やった本人でもないのに、子どもの様に誰か・何かのせいにしたくなってくるのでしょう。他責にはしってしまうのです。
他責にはしると、子どもの成長の機会が奪われてしまいます。自己中心的になってしまったり、嘘をついたり、責任逃れをしようとしたり、、、それでは、今後もトラブルが減るとは言い難いです。
お家の方の言い分、愚痴などは、大人の世界だけにとどめておきましょう。事実は潔く認め謝る、その姿を子どもに見せてあげてほしいです。その姿こそが子どもにとって何よりの学びです。
やってしまったことはよくないことかもしれない、でも、その子自身がよくない子ではないのです。
先生もそんなことは思っていないですよ。それよりも、やってしまった後のことの方が大事だと考えているのです。
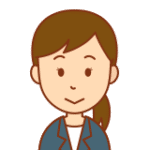
他の子たちが危険なことをしていることを目撃した場合は、みんなに注意しながらも、先生にも共有という意味で連絡帳で知らせておくとよいです。
連絡帳の使い方もご参考ください。
トラブルに巻き込まれた時
登下校のトラブルが気になるようであれば、担任に相談するとよいです。しかし、連絡するだけでなくご家庭でできることをどんどんやっていくのがよいでしょう。
それが、早期解決につながります。
登下校に関するトラブルでは基本保護者の方同士でやりとりすればよいです。また、登下校の様子を見に行き、直接相手の子に注意してもらったらよいでしょう。
気になることは、それが続いたりしないかということです。内容が許容範囲内なら様子を見るのもよいです。その時だけだったということもあるでしょう。話をして、相手の子が「しまった!」と思ってもらうのも一つです。
たびたびトラブルが続く時には種類があります。
・他の子もいるのに対象が同じ子ばかりになっている
・ただ近くにいる
・惹かれる要素がある
お家の方がその子や保護者の方に直接するのはどうしても難しい、話をしたが何度言っても改善されないというのであれば、先生に連絡をして話をしてもらうようお願いしてみましょう。
いつもトラブルに巻き込まれてしまう!と感じておられるお家の方に今一度考えてもらいたいことがあります。
トラブルにまきこまれないお子さんは、まきこまれていないということです。
しかし、登下校は下校ルートが同じで、同じメンバーになってしまいがちのため、同じ子がトラブルに合いやすいということがあります。対応を誤ると長引くことがあります。
クラスであれば、距離を置く、関わらないという選択肢もとりやすいですが、登下校となるとそれが難しくなることもあるのです。
特に下校グループがつくられている(いた)学校であれば、一緒に帰るものだと固定概念ができてしまっているこがあります。
子どもだけでなく、保護者もそう考えてしまうこともあるくらいで、距離を置きづらくなり、トラブルを繰り返してしまいます。
・なぜ一緒に帰ってくれない!
・仲間外れだ!
となってしまいがちです。
まずは、距離を置くことについてお子さんとじっくり話をするとよいでしょう。
距離を置こうとすることが悪いことだと認識してしまっていることもあります。距離を置くのは大人でもあること、仲間外れや一人ぼっちにさせることの違いを、そのお子さんの理解に合わせて話してあげましょう。
周囲に流されたり、引きつけられて、自らトラブルにとびこんでしまう子も多いです。その場合は、どうしてそのようなことになったのかを説明してあげる必要があります。
自分を振り返って理解するのは難しいかと思いますが、あの子は一緒にいたのになぜ巻き込まれなかったのかなど、比較してみるのも一つです。
トラブルに巻き込まれるまでの経緯を順を追って細かく思い出させ、どうしたら同じようなことにならないのか、お子さんの言葉でお話ししてもらいましょう。
この場合気を付けなければならないことは、お家の方の前では自分の都合のよいように話すことが多々あるということです。本人に悪気はないのです。
全てあったことを順に抜かさずに話すということが前提となります。
真相を知りたいのであれば、お家の方が付き添って登下校の様子を見ることが一番でしょう。1回や2回では本来の姿が出ないので、見えてこないかと思います。
お家の方が下校中に当たり前にいる状況にすることで、子どもたちの様子がわかり、どうしてトラブルが起こっていたのかなど原因がつかめるかもしれません。また、事前にトラブルをおさえることもできます。
登下校まで付き添うのは大変かと思います。しかし、見ないことにはわからないというのも事実です。気になるようであれば、付き添いも検討してみてください。
まとめ
登下校のトラブルは、大人が付いていないので余計に心配になると思います。トラブルが継続すると尚のことでしょう。
トラブルを起こしたときも、巻き込まれたときも、冷静になることが必要です。解決したいことは何か、これからどうしていくとよいか、トラブルをどう成長につなげていくのか、そこまで考ていくのが大人の役割です。
- 大人としての対応を子どもに見せていくことが大切
- 一緒に付き添って登下校する気概が必要
安全に登下校してもらうのが一番ですので、保護者の方のお力が必要となります。
ご理解いただけたら、お家の方も、「学校が何もしない!」という変な怒りやもやもやから解消されるのではないでしょうか。
学校と保護者は、手を組んでいくチーム?仲間?同志?のような関係ですので、怒りの感情で付き合っていては、お子さんにとってもよいことはありませんよね。
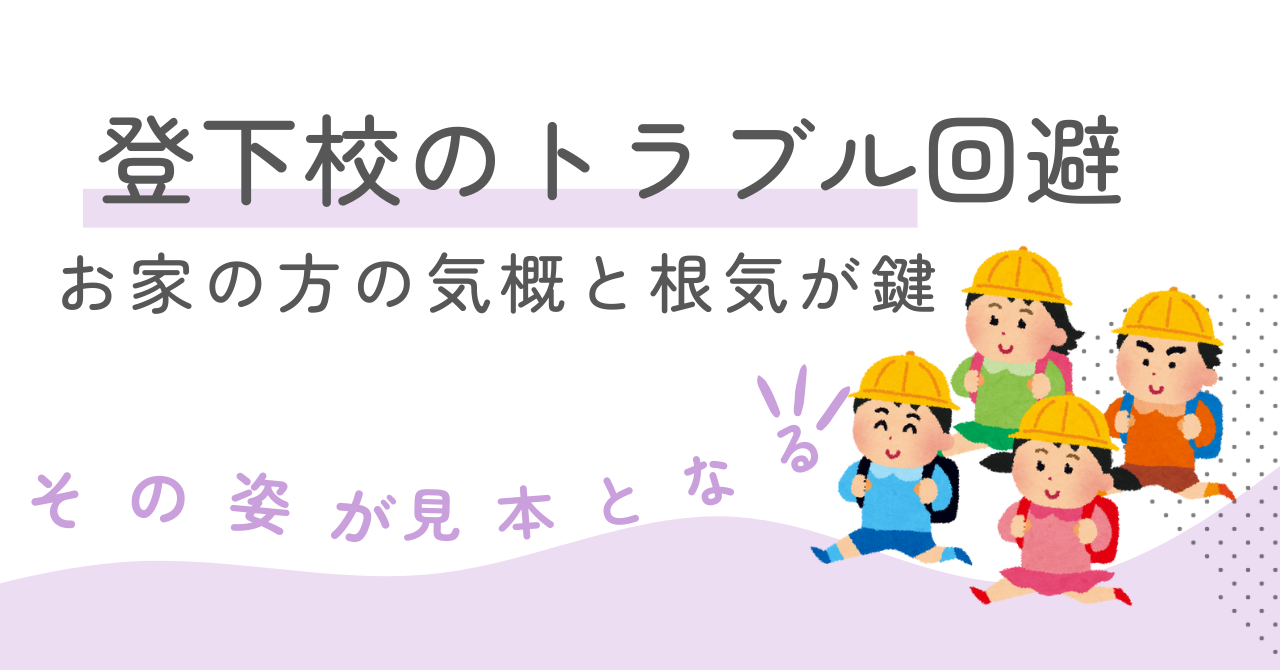
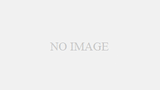
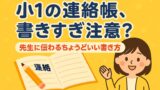
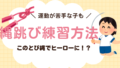
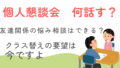
コメント