「4月は頑張って通っていたのに、GW明けから“学校に行きたくない”と言い出した…」
そんなお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
1年生にとって、GWはようやく慣れてきた学校生活にブレーキがかかる一つの節目です。
GW明けに1年生がしぶることは実はよくあること。
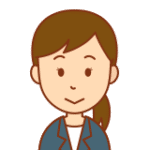
教員歴20年以上、1年生担任8回で250人以上見てきた教員が、GW明けに学校を嫌がる理由と、家庭でできる3つの対策を中心に、保護者が気をつけたいポイントを紹介します。
なぜ1年生はGW明けに「学校へ行きたくない」と言うの?
GW明けと、夏休み明けは、担任としても気にかけます。冬休みはその心配はなくなります。GW明けと夏休み明けにしぶりが出るとわかっているからです。
GW明けに学校を嫌がる言動が出てくる理由は主に2つです。
4月の緊張と疲れの反動が出やすい
4月は環境の変化と初めての小学校生活で、心も体も疲れがたまっている状態。
GWはその緊張が一気に緩むタイミングであり、疲れや不安が表面化しやすいのです。
友達も先生もはじめましての人たち。子どもながらに周囲の人たちの様子を伺っています。自分自身を出しきれないこともほとんどです。
やり方やルールなども一つ一つ覚えていきます。
・かばんの扱い
・給食のもらい方
・学校の日常用語(連絡帳、ロッカー、教科書、ノートなど)
・トイレに行くタイミング
やることは園と同じでも、やり方が少しずつ違います。
一つ一つ教えてもらっても一回では覚えられません。4月に何度も繰り返して覚えていきます。わからない時は周りを見ながら真似をします。
何気なく生活していても、頭はフル回転ですね。GWには、その疲れがどしっと出てきます。心も体も解放されるのです。
「学校=がんばる場所」というプレッシャー
1年生は「勉強=がんばるもの」「学校=ちゃんとするところ」という意識が強くなりがち。
真面目な子ほど、学校に戻ることがプレッシャーになることもあります。
つい1か月前まで、園で遊んでばかりだった、動き回っていた状態だったわけです。
・1日5時間席に座る
・休み時間は数十分
・お昼寝がない
・学校の約束を守る
窮屈にも感じることでしょうね。
憧れていた小学生がこんなにしんどかったとは、面白くない、園の方がよいとは・・・と感じ始める4月中旬。しかし、流れと勢いで4月を乗り切ります。
ただ、学校生活に慣れてはきているので、このまま進めば楽になっていくはずです。
しかし、そこに連休がはさまります。GW明けの登校は、踏ん張りが必要になるのです。
GW中にできる!家庭での3つのシンプルな対策
GWは解放されるので、明けて登校となると家の方がいいと引っ張られてしまいやすいです。
しかし、うまく活用することは心身のリフレッシュにつながり、連休明けのパワーともなります。
連休の過ごし方がポイントとなります。
子どもにとっての「特別」は日常の延長+α
大人は「旅行やテーマパーク」などの非日常を特別と考えがちですが、 子どもにとっての特別は、日常のちょっとした変化でも十分。
お出かけ三昧で、体力が奪われてしまうと逆効果
例えばこんな工夫が「思い出」になります。
- 朝おにぎりを作って、少し遠くの公園へ
- サイクリングでいつもより少し遠出
- 畑や庭でのお手伝い、収穫+お料理
- 家族でトランプやカードゲームに夢中になる
- 普段NGのガチャガチャを1回だけOK!
笑顔で過ごすだけでも、子どもの心にしっかり残るのです。
最近では特に、働く方も増えて、お休みでもお忙しくされている方も多いです。
遠出をしたり、特別なお出かけをしていなくても、楽しかったんだな~素敵な過ごし方をさせてもらえたんだな~と、子どもたちの様子から伝わってきます。すがすがしい表情をしているのです。
沖縄などの旅行日記が、「ホテルのバイキングがおしいかった」「ホテルのプールが楽しかった」という内容になるのは、日記あるあるです。
子どもにとっては、どこに行ったかよりも、「何をしたか」「誰としたか」が大事なようです。
生活リズムは崩さない
起床・食事・就寝のリズムは、できるだけ学校がある日と同じに保つのが理想です。
特にGWの最終日は「登校モード」に戻すようにしましょう。
夏休みと異なり、生活リズムが崩れたまま過ごすと、通常に戻そうとする間に学校が始まってしまいます。疲れたまま、だらだらと進んでしまうことになります。
遠出をする場合は無理のない計画で、日常の生活に合わせるように心がけたいものですね。
楽しいことは、疲れていてもそのように見えないものです。しかし、まだ6歳。体力もありません。体の疲れが心に直結するので、ゆったりしたスケジュールを組んであげてください。
体を動かしてリフレッシュ「心と体の休養」を
体を動かすことで、ストレス発散・良質な睡眠につながります。
一緒に軽く外遊びやストレッチを取り入れてみましょう。一緒にというのもポイントです。
・公園で縄跳び・鉄棒の練習やボール遊びをする
・YouTubeにあるストレッチやラジオ体操などに挑戦する
・歩いて買い物に出かける
気候がよいので、外で体を動かすと気持ちも晴れ晴れしてきます。学校では休み時間や体育以外、席に座ってうずうずしています。飽きるまで、思いっきり外で遊ぶのもいいですね。
それでも登校しぶりが出たときは?
登校前夜にぐずぐず言うのは当たり前、登校日の朝にしぶることもあり得ると思っておけば、焦らずにすみます。
「共感」は土台だが保護者の心の余裕が前提
「行きたくないんだね」と気持ちを認めてあげることは案外難しいものです。
出勤時間が迫ったり、毎日続いたりすると、強い口調にもなってしまうもの。朝はぐずっているのに帰ってくると元気になっていて、なんだ!となってしまうかもしれません。
滅入ってきますよね。
共感する姿勢を見せることが大事だと理解していても難しいことです。
思いがあふれて態度に出てしまうことがあるかもしれませんが、そのような時もご自身を責めないでくださいね。それも、よくあることと思ってください。
ご自身の心に余裕を持たせてあげることが、お子さんへの共感につながります。
「おまじない」やスキンシップも効果的
手をさすりながら「がんばれるおまじないかけようね」と声をかけておられる保護者もおられます。
掌に絵を書いてあげている保護者もおられます。子どもは授業中に手に書いてあるマークをひっそり見ています。いつしか、自分で書いていました。そして、そのうちなくなりました。
毎朝スキンシップをとりながら、応援しているからね!と送り出している姿を想像します。
安心感が高まり、一歩踏み出す勇気が出る子も多いです。
数日すれば慣れることもあるのでどしっと構える
「5月は再スタートの月」
焦らず、少しずつ学校に慣れていけるよう、見守る姿勢を大切にしましょう。
学校でも、焦らずぼちぼちスタートさせます。
入学後、少し学校生活に慣れてきました。しかし、GW明けの5月、先生は一からのつもりです。
・やり方やルールなどを忘れている
・久しぶりに会うので緊張感が高まっている
・のびのび生活と学校生活とのギャップに疲れが出る、気分がのらない
このようの状態はわかっているので、再スタートのつもりで進めていきます。保護者の方も、そんなものだと思っておくと少し気が楽になるかもしれません。
登校しぶりに焦らなくて大丈夫
登校しぶりは、GWに限らず1年間を通して見られることがあります。
よくある対応例としては
- 保護者と一緒に登校
- 時々お休み、時々遅刻
- 集合場所まで送り、近所の年上の子にお願いする
朝は嫌がるけど、学校では元気に過ごしていることがほとんどです。お子さんの性格や家庭の雰囲気に合わせて、押したり引いたりでOKでしょう。
・働いていてそこまで構っていられないから、対応が丁寧にできない
これはこれでよかったりもします。子どもが行かざる得ない状況が後押しとなることも大いにあります。
・優しすぎる?もう少し厳しくしくした方がよいのか
これはこれでよかったりもします。
保護者や家庭の雰囲気、今までの状況が違うので、他と比べる必要もないです。正解はありません。
保護者の方と子どもの様子を見ていて、大事だと思うことは、どなたかに預けた時に泣いていてもさらりと離れることです。
NG思考になると、原因を特定しようとしたり、誰かのせいにしようとしたりするので注意が必要ですです。
・なぜ我が子だけ?
・学校で何かあるの?
・何が理由?
・いつまで続くの?
焦りや不安にかられるかと思いますが、長い目が必要です。
保護者があたたかく見守り、関わり続けていればお子さんにも伝わります。
先生の本音としては、
「学校まで来てくれたら、あとはなんとかなります。大丈夫です。」
重大な理由で渋る以外は、1年生ではとにかく学校に身をおくということが、大抵の場合一番の解決に感じます。
遅刻や欠席が定期的にある場合、先生もしぶっていることに気づいてくれているでしょう。
学校での様子が心配であれば尋ねてみるとよいです。楽しく過ごしている様子を知り、安心される保護者も多いですよ。
ご自身の気持ちがいっぱいいっぱいになる前に、先生に相談してくださいね。
急を要さないのであれば、懇談会など何かの機会に知っておいてもらうというのもよいですね。
まとめ
ゴールデンウィークは楽しい反面、子どもにとっては疲れや不安も出やすい時期。
日常の中で「休む」「整える」「少し動く」を意識することで、登校しぶりをやわらげることができます。
お子さんの反応は「自然なこと」
焦らず、優しく寄り添ってあげてくださいね。
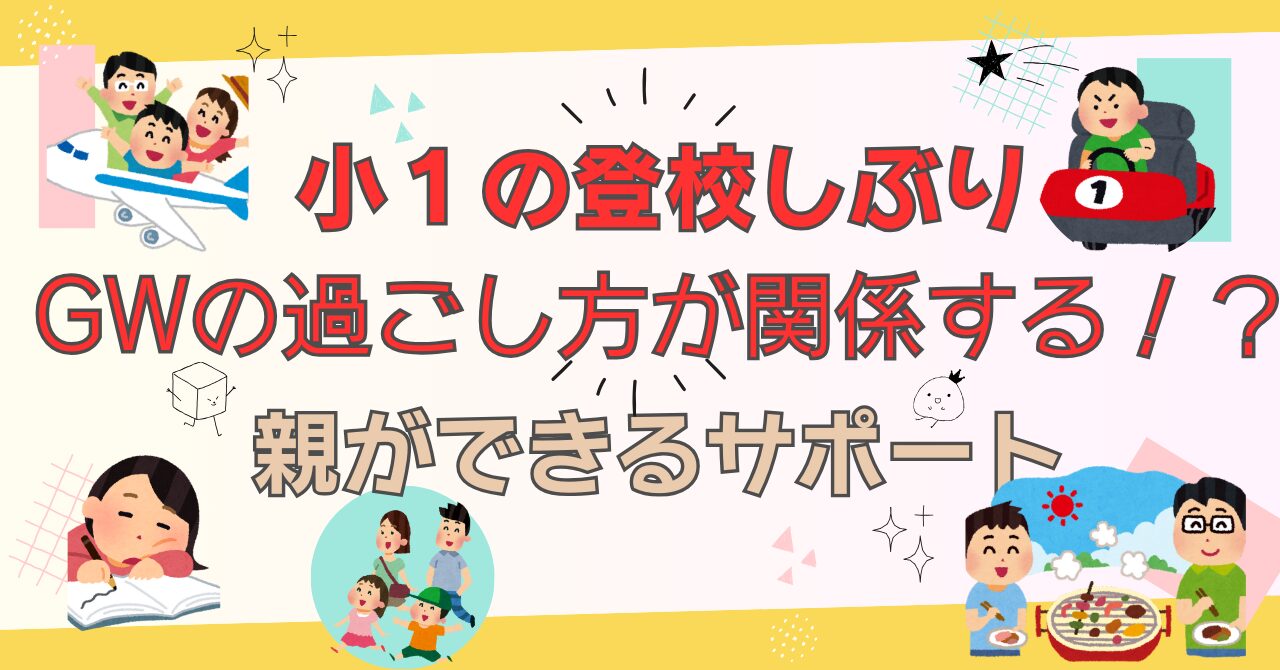
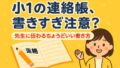

コメント