1学期間が終わり、成績表をもらった方がほとんどのことでしょう。
その成績表、どのように付けているか気になりませんか?
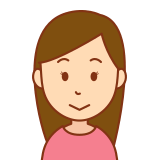
あれ、今年は甘い?昨年は厳しかった?
このような声を聞きます。
保護者の方は成績の付け方の基準がわからないので様々な疑問をもちますよね。
成績付けの基準は、国の指導要領をもとに、学校や学年、もしくは市区町村で決めます。いくら基準があっても、付けるのは先生=人、主観が入ります。

成績の付け方、先生の迷いなど、教員歴20年以上、1年生担任8回の教員が、成績付けの裏側をお伝えします。
今までとは違う視点で成績表を見ることができ、夏休みの学習課題のヒントになるかと思います。
成績はテストの点数が基本

成績を客観的に付けるために、テストの点数が重視されやすくなります。基本はテストの点数です。
基準を学校ごとにつくります。だいたい、市区町村で似てきます。
- 90点以上で◎
- 80点未満で△
基準点が学校ごとに異なるだけでなく、学年でも相談して、学校基準の点数の前後に変更することもあります。大幅には変更しません。
あまりにも◎が多い、あまりにも△が多いと、この基準を検討するのです。
テストは、学校や学年、そしてその年によって、採択する会社が異なります。4月にいくつもある会社からサンプルが送られて選ぶのです。
似たり寄ったりの内容ですが、少し尋ね方が簡単な会社であったり、発展的な問題が入っているテストだったり、様々なのです。
子ども達の実態や、テストが難易度などを踏まえて検討しています。
成績表の項目(観点)は各教科ごとに3つあります。
- 知識・技能
- 思考・判断
- 主体性
テストの点数欄に、小さく記されています。テストでは下記のようになっていることが多いです。
知識・技能
- 国語:テスト裏の言語に関数する内容
- 算数:テスト表の計算や覚えているかという内容
思考・判断
- 国語:テスト表の文章を読んで答える内容
- 算数:式など少し考える応用的な内容
主体性は、裏の最後に出題されることもあります。
しかし、加味するかどうかは学年に委ねられますし、加味されたとしても割合は低い傾向にあります。
授業での課題も加味される

テストだけ評価するわけではありません。
- 作文や詩(国語)
- 答えを導き出すまでの考え方・説明の仕方(算数)
- わかったことや気づいたことなどの感想
発言やノート、課題プリントなどで見ていきます。
感想というのは、長く書けばよいというわけではありません。
その課題に沿った感想です。
しかし、上記のような評価は、基準を決めても主観が入ってしまいやすいです。
条件を入れて書かせても、採点者(担任)によってもぶれてしまいます。
ですから、授業中に評価はするとしても、成績表には加味程度にする学年もあります。
担任の独断にならないように、学年で相談します。
基本はテストで、その後の判断材料にするということです。

テストの点数で評価するとぎりぎりラインだわ。学習の中の課題はできているから上げようかしら。
割合で決めることもあります。
テストの点数を8割入れて、課題を2割とした場合の点数を出すのです。
低学年の成績は甘くなりやすい

低学年では、学習内容や評価の基準、そして、先生の思いから甘口評価になりやすい傾向があります。
先生の思いという時点で、主観が思いっきり入っています。
しかし、低学年でも、しっかりと△を付ける学年もあります。

できると思われても、このままでは中学年・高学年でひっかかって困ることになるわ。
”自信を持たせることと=評価を甘く付けること‘‘ではないということですね。
適切に付けることが子どもたちにとって大事だという考えるからです。
生活科はテストがなく曖昧
低学年は、生活科がテストではありません。生活科カードが主になるので、先生の采配がしやすいのです。

カードはできていないけど、尋ねたら返答できたし、〇にするか…
生活科で評価が低くなりそうなお子さんは、国語や算数ですでに△が付くことが多いので、「生活科くらいは」という気持ちが働きます。
これも主観ですので、独断的にならないよう学年で相談します。
体育・音楽・図工は目標が低い
体育や音楽、図工は、よっぽどでない限り△になりにくい内容です。
- 楽しく
- 安全に
- ルールを守って
- 表現する
しかし、課題がはっきりとしている内容は△がしっかりと付きます。
- 合格ラインに達していない(跳び箱・鉄棒・縄跳び・鍵盤ハーモニカなど)
- 表現できない(歌わない・作らない)
- 表現しても伝わらない(聞こえない・何かわからない)
- 不器用(はさみ・のり・塗り方)
- ルールがわからない、守れない
しかし、どれか一つの課題だけで△を付けません。跳
び箱が△でも縄跳びがとても上手であれば、体育としては〇になることがあります。
こういった課題の基準は学校や学年で決めます。
1年生1学期の成績で△は要注意
1年生1学期は、入門期ですので、基本的には成績は全部◯にしてあげたいところです。
入学前に身に付けた力で左右されやすいからです。
しかし、できていないのに◯にするなど適切に評価しないと後々困ります。特に国語と算数です。
国語と算数は他の教科に比べて、現実的に付けることが多いです。
1年生でも国語や算数の成績で△が付く場合、下記のような学習状況が見られます。
- ひらがな50音を読めない・書けない
- ひろい読みをしている
- たし算・ひき算で数え足し・数え引きをしている
ひろい読みとは、言葉のまとまりで読まずに、一字一字で読むことです。

音読で読めていると思っていたら覚えてしまっていたということは、1年生でよくあることです。
数え足し・数え引きというのは、手を使う時に一つずつ順に数を足していったり、引いていったりすることです。
6+3をする時に、ぱっと指を6にせず、1から順に6まで数えて出し、そのあと、ぱっと3を足さずに、1・2・3と順に足していくということです。
数のまとまりがまだわかっていない段階です。
テストで下記のような課題ができていない場合も点数がのとれず△になりやすいです。
- つまる音やのばす音、ねじれの音を間違える(作文などでは多少間違ってもよい)
- 国語の本文から抜き出せない(テスト表側の文章題)
- たし算とひき算の式を区別できない(主にテスト裏側の文章題)
テストと言っても、1年生1学期のテストは、授業中に学習した内容のままです。
答えの欄がわかりやすくなっていたり、絵からわかるようになっていたり、工夫されています。
もし、△が付いているのであれば、何かしらの手だてを夏休みにしてあげた方がよいです。
今まで見てきて、何もせずにいて様子を見ているだけで学習内容が追いついたお子さんはおられません。

クラスの半分以上が早生まれのクラスもありましたが、成績に関して早生まれなどは関係なかったです。
成績に関するよくある誤解3選

兄弟や前年度と比較されたり、自分の頃と比較されたりするお家の方もおられますが、誤解されている方も多いようです。
誤解①中学年から成績が厳しくなる
中学年から厳しくなったと感じるのは、以下の点からです。
- 低学年が甘かった
- テスト(学習内容)が難しくなった
単に学習内容が難しくなるのです。
よく9歳の壁と言われます。抽象的思考が十分に発達していないと、内容についていくのが難しくなります。
具体的で日常的な内容から、抽象的な概念や応用的な思考が必要な学習が増えるのです。
この9歳の壁を超えれるか超えれないかで、学習の理解度が変わってきます。
特に生活力のあるお子さんは、今までなんとなく直感で解けていたということがよくあります。
中学年になり、抽象的な難しい課題になった時に、低学年の内にどれだけ力を蓄えてきたかにかかってきます。
- こなすだけでなく、低学年なりの意味理解をしようとしてきたか
- 先生や友達の話を理解しようとしてきたか
- 知っている内容、知らない内容に関わらず集中することを身に付けてきたか
- わかりたい!できるようになりたい!と向かっていけたか
- 最後までやり切ろうとくらいついていったか
抽象思考はすぐに身に付くわけではありません。上記のような力を使って、乗り越えていくのです。
誤解②◎△の人数は決まっている
昔はこのような付け方でしたが、今は違います。人数ではなく、基準に達したかどうかです。
しかし、あまりにも人数に偏りがある場合は、基準が高い、もしくは低いということで、その基準を上げたり下げたりして、再度調整することがあります。
90点以上を◎にしたら30人中28人が当てはまった
→適切な点数基準ではないのではないか?と考える
95点以上を◎にしたら8人になる
→妥当だとなれば◎は95点以上にする
点数基準の調整の際に、授業での学習課題も判断材料となるのです。
点数基準を調整しますが、◎や△が多くても、少なくても、付ける時には付けます。
△の人数が多くても、できていない判断したら付けます。
◎の人数が多くても、力が付いていれば付けます。
妥当かどうかという判断は、先生たちが決めているので主観とも言えます。
誤解③ノートや挙手を頑張れば成績が上がる
昔の「関心・意欲・態度」の項目が、「主体性」という言葉に変わりました。
昔、下記のように言われませんでしたか?
- たくさん発表する
- たくさん感想を書く
- きれいな字でノートを書く
- 頑張っているところを見せる
今はそれで〇が◎になったりしません。できたか・できていないかです。積極的というだけではないのです。
しかし、先生たちが一番付けにくい項目なのです。「主体性」を何で評価をとるのか、どこで評価をとるのかが非常に難しいのです。
成績を付けるときに、非常に曖昧になりやすい項目です。まさに主観になりがちです。
主観が大きくなるため自信を持って付けられない分、◎や△には慎重になります。

主体性を◎にすると、オール◎になるなあ。本当にこの教科、完璧かしら。
△を付ける時は、よけいに気をつかいます。理由をはっきりと説明できないのに付けにくいです。
「主体性」の考え方は、自分の力をのばすために、適切な方向に向かって努力できているかどうかです。
いくら頑張っていても、方向性が違えば「主体性」が◎にはなりません。
課題解決に向けて、誤りを修正しながら学習できているかどうかです。
「他の知識・技能や思考の項目が△であれば、課題解決に向けて修正できていないので、◎ではないよね」という考えです。
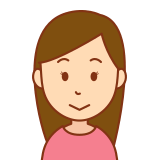
テストが悪かったら、頑張っても◎にはならないということ?!

そうですね。ただ、主体性が本来は△であったのを、〇にはしてもらっているかもしれません。
成績は主観が入るもの
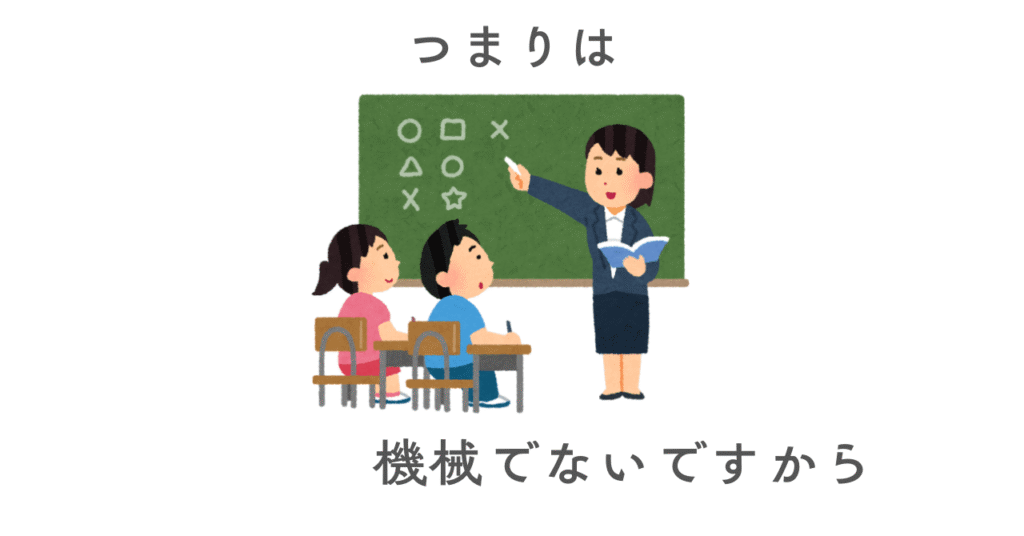
学校や学年でどのように評価するか基準は決めますが、テストの点数のようにはっきりしているものであっても主観は入ります。
人が成績を付けている以上そうなります。
ましてや、テストがないものは主観でしかありません。
テストがある教科の成績
テストでさえ、検討事項が学年の考えで変わります。
- 減点にするか、〇にするか、点数なしとするか
- 小テストを成績に入れるか、練習とするか
- 漢字まとめテストを実施する前に配布して練習してから挑むか、配布しないか
- 何点までを◎とするか、何点未満を△とするか
どれがよいではなく、それぞれにそれぞれのよさがあり、考えがあります。
テストがない教科の成績
テストがない評価は基準を決めていても主観になってしまいます。
以下のような内容だと評価が付けやすいです。
跳び箱:4段が綺麗に跳べたら◎,3段が跳べないと△
縄跳び:前跳び20回と後ろ跳び10回で◎,前跳び10回以下と後ろ跳び5かい以下で△
鬼遊び:ルールを理解できなかったり無視したら△
鍵盤ハーモニカ:5曲中全曲タンギングでふけたら◎,5曲中3曲ふけなかったら△
歌唱:歌わなかたり聞こえなかったら△
しかし、鬼遊びで◎は付けにくいです。
評価の基準を決めていても、その場に応じて刻一刻と変化する中で、「〇〇していたら◎」という条件で、全員を把握できないからです。
今は、タブレットで撮影して後から見返すということもできますが、アップでないのでわかりにくいですし、発言も聞こえませんので、その子がどうしてそのような行動をとったのかまでわかりません。
「〇〇していたら」という条件自体が曖昧になります。
音楽でめあてに沿って歌を歌い、そのめあてが達成できたかどうかも、正直音楽の専門家でない限り、聞く人によっても変わりますよね。
成績がやばい!家庭でのフォローの仕方
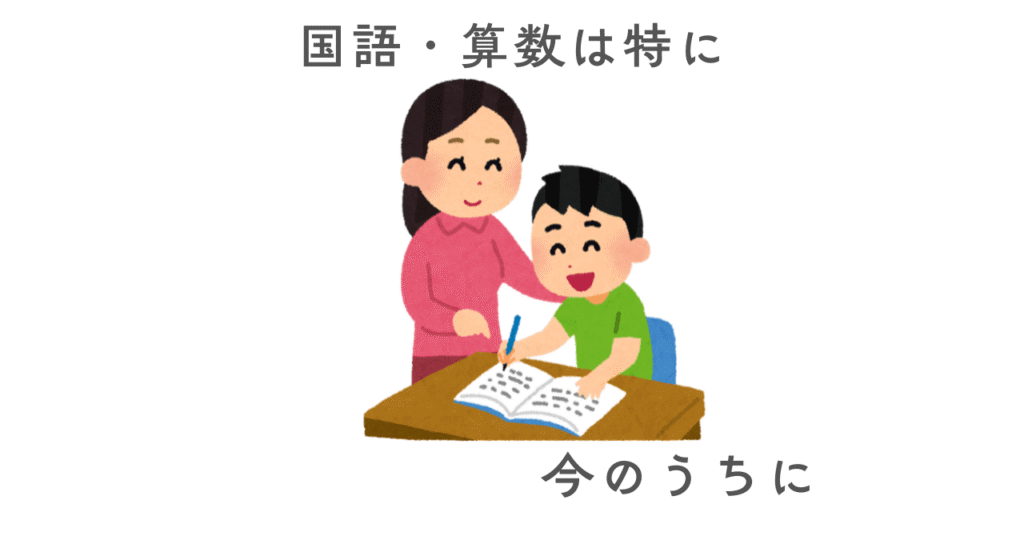
学校や学年で基準を決めていても、人が成績を付ける以上、主観が入るものです。
様々なことを考慮した上で主観が入っていると認識し、成績表を活かしてほしいです。
◎が付いた場合は喜んだらよいです。努力が評価されると嬉しいですよね。
その一方、お子さんが◎が増えた減ったで一喜一憂しないように、すごいね!頑張ったね!その調子で!と、過程を踏まえて励ましてあげてほしいです。
気を付けてほしいことは△がある場合です。教科によっても、気を付け方が変わってきます。
国語・算数は第一に
積み残しがあると、そこを解決しないと追いつきません。夏休みの間にフォローしておきましょう。
あれもこれも難しいので、絞ることが大切です。
2年生以上は、1年生のドリルからやることが近道です。算数は1年生・2年生でひっかかかっていることがほとんどです。
1年生は、ひらがな50音とたし算・ひき算の計算の習得をまずは目指しましょう。
下記の記事は、大人気のポケモンずかんドリルの紹介をしています。
年長さん向けだけでなく、小学生用があります。国語の他に、算数もあります。算数は分野ごとに分かれているので、お子さんに合わせて選択しやすいですよ。
国語の1年生用は、ひらがなとカタカナが合わせて練習できるのが秀逸です。2学期の予習になります。
理科・社会・体育はまだ大丈夫
学習内容が学期によって変わるので、挽回の余地があります。
体育は△を気にするよりも、少しでも楽しい内容、できる内容が増えるといいですね。
たとえ〇にならなくても、頑張った分だけ成果としてわかりやすいので、一緒に練習して自信を持たせてあげるとよいですよ。
特に、体育が苦手なお子さんでも、根気があるお子さんに向いているのが縄跳びです。
音楽は鍵盤ハーモニカ・リコーダー
音楽で成績がよくない場合は、鍵盤ハーモニカやリコーダーの場合が多いです。できているか、できていないかが明確だからです。
楽器ができないと音楽の時間の楽しさが半減、もしくは嫌になるので、もったいないです。音楽の授業で費やす時間が長いからです。
早めに練習してマスターしてしまった方が、気持ち的に楽でしょう。

初めて小学校で鍵盤ハーモニカを触ったお子さん。不器用で、四苦八苦してましたが、家庭での練習を頑張り続けました。結果、テストを1回で受かるようになりました。
できないまま練習をだらだらしていると、不合格の曲がどんどん増えてしまい、苦手に感じてしまいます。
毎日数分、触る癖をつけておくと上達します。
図工はとにかくほめる
図工で△が付いた場合は、「自分は下手だから」と思わせてしまってはかわいそうです。
のりの使い方、はさみの使い方、塗り方など、技術面を練習したら大丈夫だと教えてあげましょう。
表現した作品自体を否定してしまうことがないように、作品自体は素敵だということを伝え続けてほしいです。
まとめ:あれこれ考えぬいて主観が入る
成績表って、どうやって付けているの?という疑問。
テストの点数を基本に、学年で話し合いながら付けます。
正直、「これは主観が入るよな…」「どこまで甘くしていいんだろう…」と迷うこともあります。
1年生の1学期の△は、実は担任にとっても覚悟の△。
「まだ1学期、でもこのままではまずい」と付けます。
だからこそ、成績表の付け方を知ることは、夏休みに何をサポートすべきかを知る手がかりになります。
「うちの子、頑張ってたのになんで△?」「1学期から△が付いた!」と悲観的になることではありません。裏側を知れば、先生の見ている「伸びしろ」が見えてくるはずです。
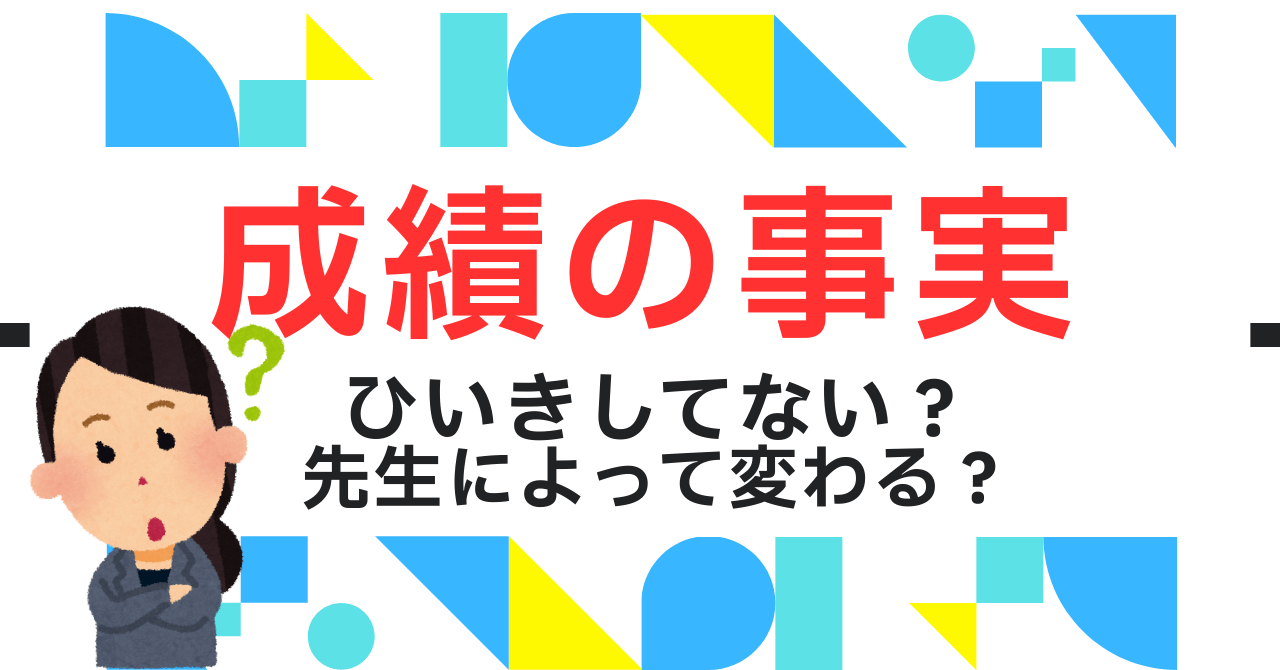
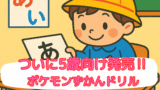
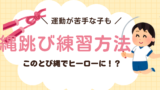

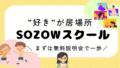
コメント